目次

監修者プロフィール
浴野 真志株式会社Groovement 代表取締役
- ・デロイトトーマツコンサルティング、Field Managementにて、 主にB2C領域におけるマーケティング戦略、新規事業の検討、各戦略の実行支援に従事。
- ・2021年に当社を創業し、フリーコンサル向けの案件紹介マッチングサービス
「Strategy Consultant Bank 」をローンチ
編集・構成について
本記事は、コンサルティング領域に精通した外部ライターによる寄稿内容をもとに、
株式会社Groovement編集部が構成・編集を行っています。
公開前には事実確認や信頼性のチェックを行い、正確な情報提供に努めています。
運営会社情報
- 運営会社:株式会社Groovement
- 許認可:有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-316145)
- サービス名:Strategy Consultant Bank
※記事内容に誤りなどがございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
Related Article
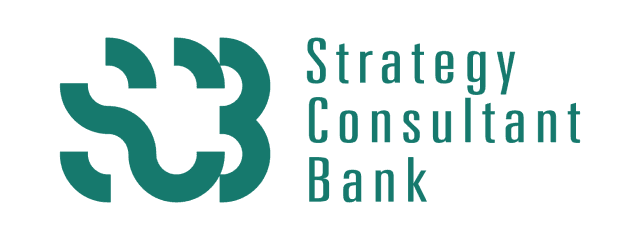
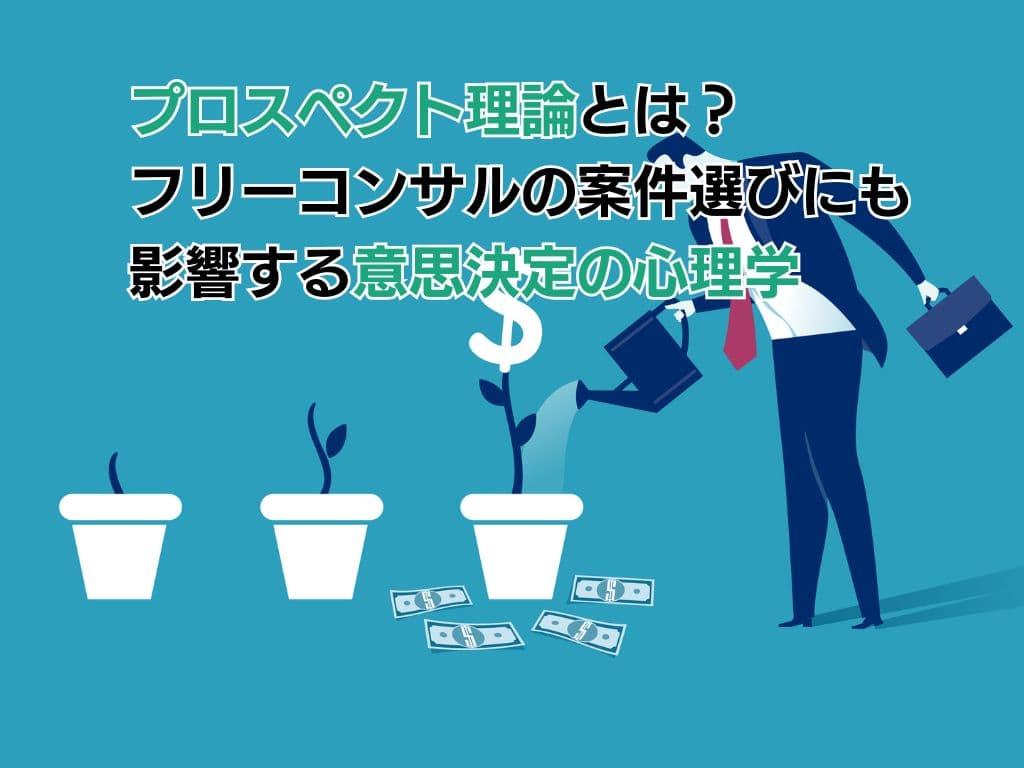


.png&w=1200&q=75&dpl=dpl_DXZHRKdWpwy1Y6FJxheqdk3AQEh7)
